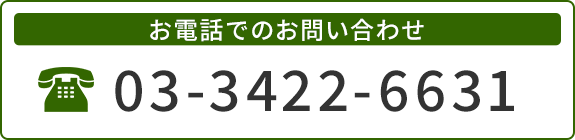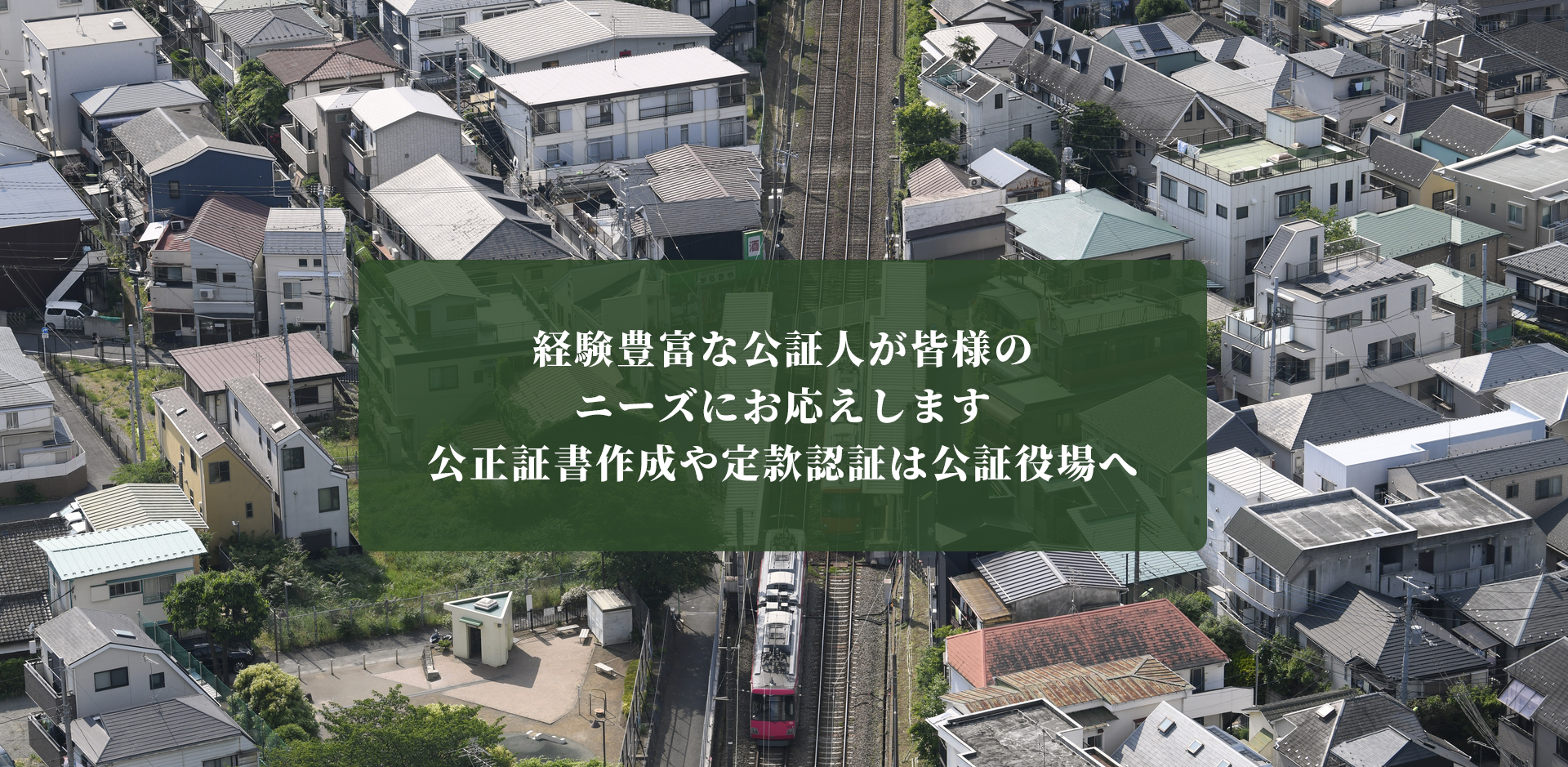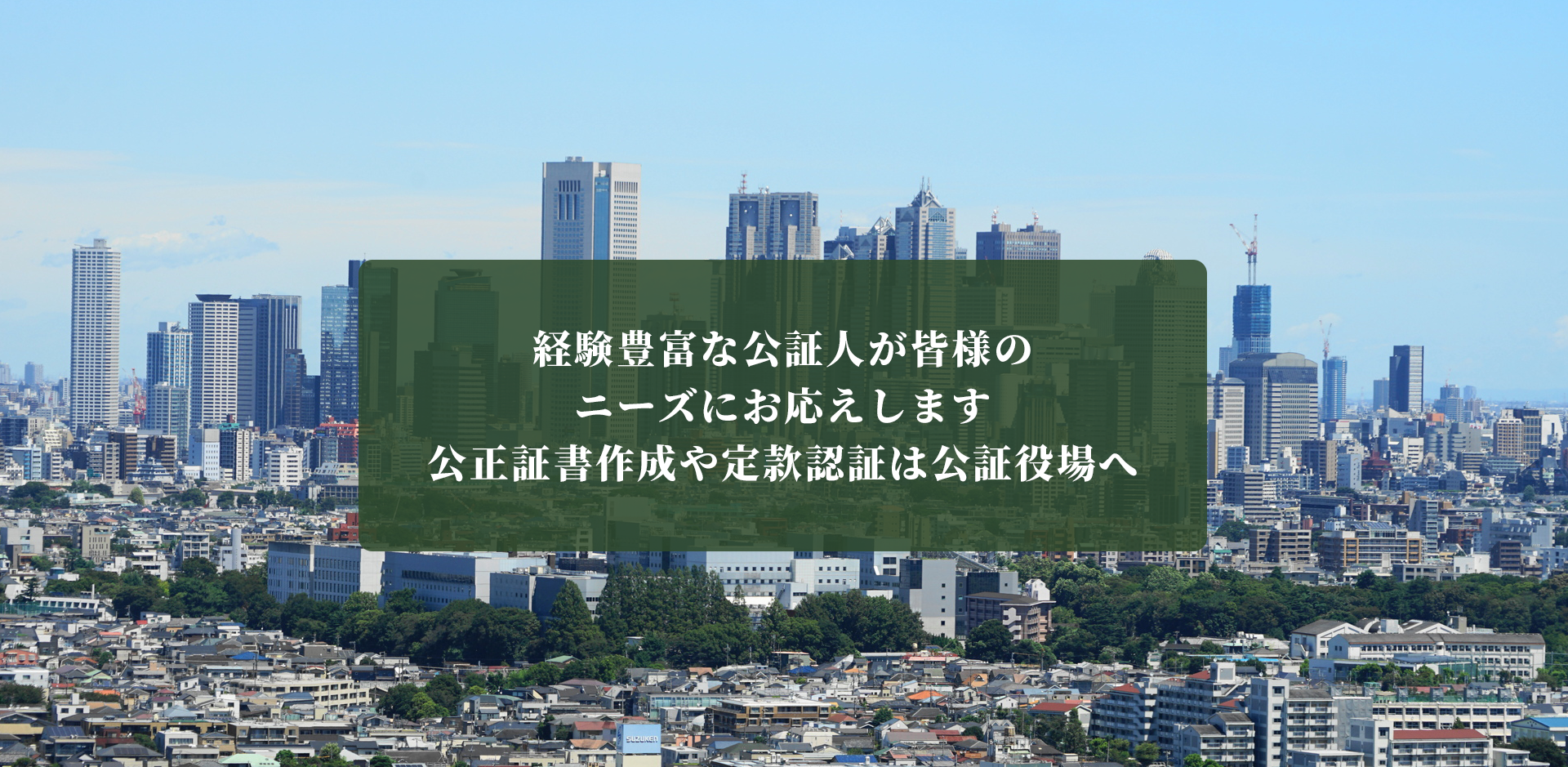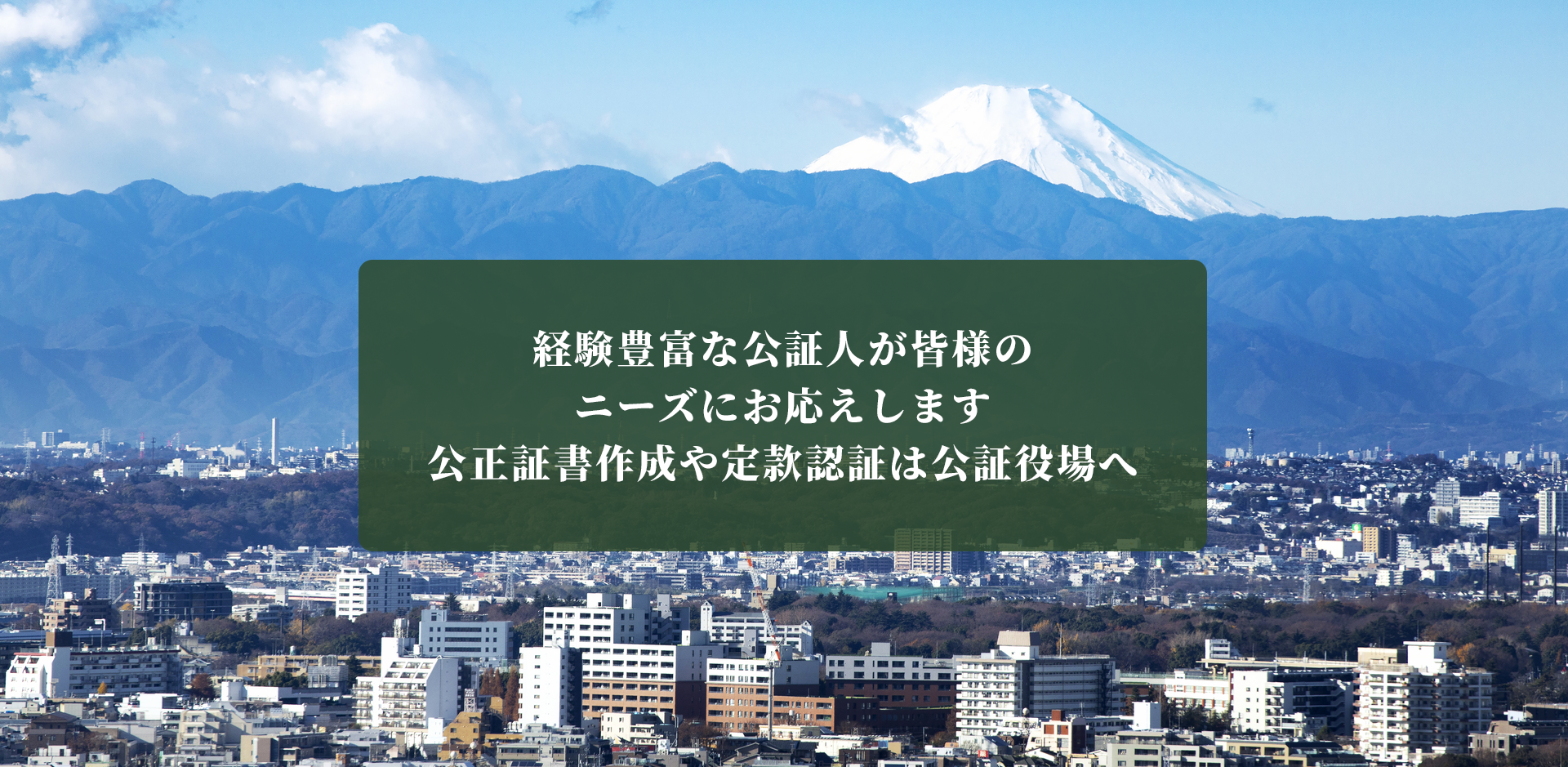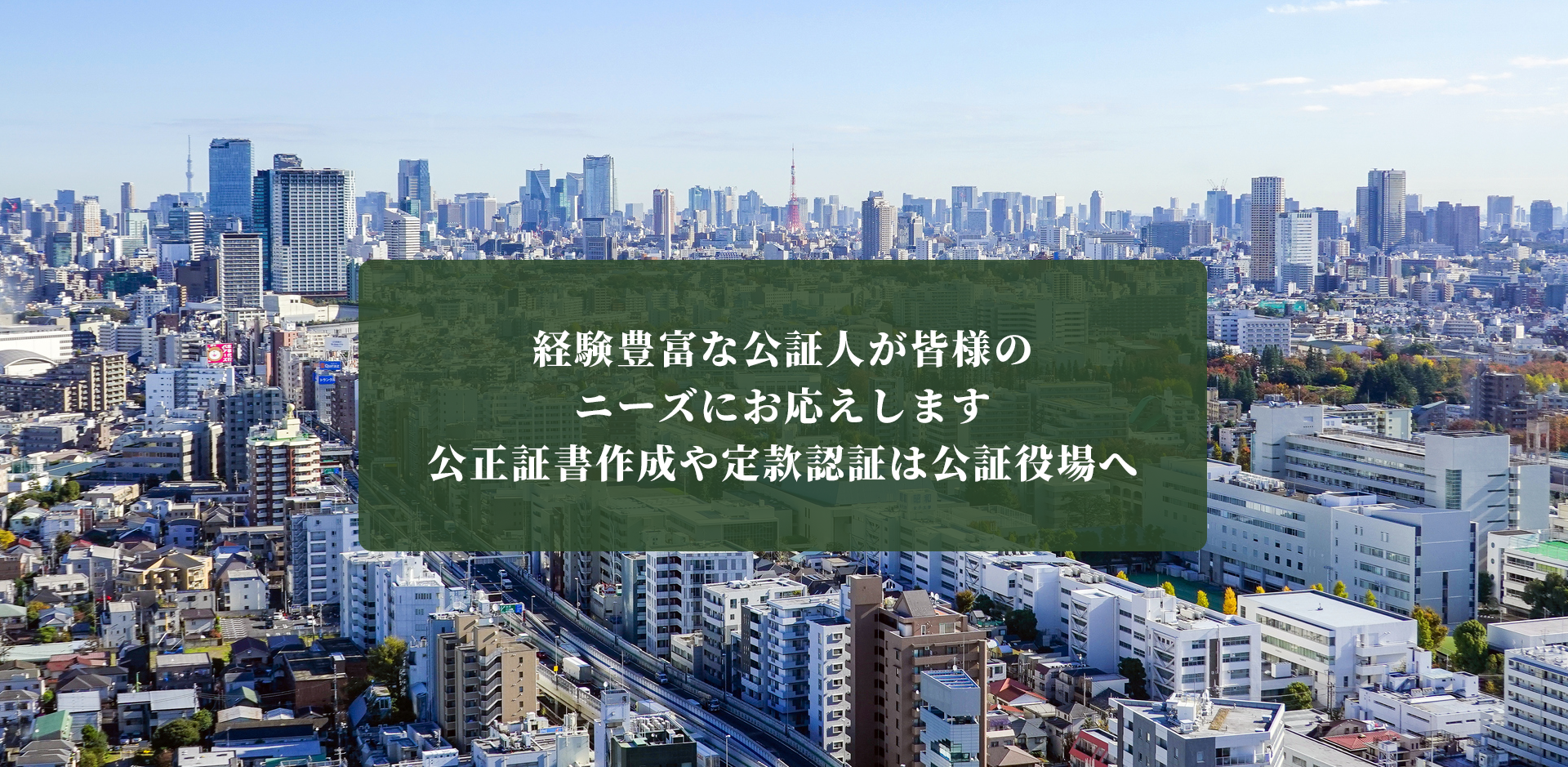ご案内
世田谷公証役場では、お待ちいただく場所が限られており、また、お客様の対応を適切にさせていただくためにも、当公証役場にお越しの際は、完全予約制とさせていただいております。
予約制の趣旨をご理解いただき、お手数をお掛けしますが、事前に電話等でご連絡いただき、予約の上、当公証役場にお越しいただきますようよろしくお願いいたします。認証、遺言検索等をご希望の方も、事前に電話等でご連絡いただき、予約をお願いします。また、確定日付の付与につきましても、お越しになる当日でも結構ですので、事前に電話等でご連絡いただき、予約をお願いします。
営業時間
当役場の営業時間は、平日午前9時から午後5時までです。
午後零時から午後1時までは昼休み時間とさせていただいております。
休業日
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで休業)
新型コロナウィルス感染防止対応等(令和5年5月8日更新)
現在、当公証役場におきましても、公証業務を適切に継続するため、日本公証人連合会で定めた「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引」(2023年5月8日)等に基づき、新型コロナウィルス感染防止の観点から、アクリル板を設置するなどしているほか、特段の事情のない限り、体温測定や手指の消毒等をお願いしております。
また、当公証役場は、訪問者の多くが高齢者であることや対面での会話を伴う業務であることなどもあって、公証人等は引き続きマスクを着用しており、また、お客様におかれましても、当公証役場をご利用の高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、アクリル板等の感染防止設備のない場所での、対面での会話を行う場面では、マスクの着用をお願いしております。
さらに、対面での手続は、最小限かつ短時間にすべく、原則として、当公証役場にお越しいただいての対面でのご相談等は行っておらず、郵送や電話、メール等の方法により、ご相談やご質問等に対応させていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
そのほか、当役場では、訪問者の待合スペースの混雑を避け、お客様の対応を適切にされていただくためにも、予約制とさせていただいていますので、お越しの際は,事前に電話等での予約をお願いいたします。
従前より多少お時間をいただいていますが、お急ぎのときなど特段の事情があるときは、ご連絡ください。
なお、「お知らせ」にも、記載してありますが、遺言の公正証書と任意後見契約の公正証書の作成については、当公証役場オリジナルの手引を作成しましたので、ご希望の場合は、ご連絡ください。
ホームページ案内
5手続案内
公証役場概略
| 役場名 | 世田谷公証役場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8ファッションビル4階 |
| TEL | 03-3422-6631 |
| FAX | 03-3487-5925 |