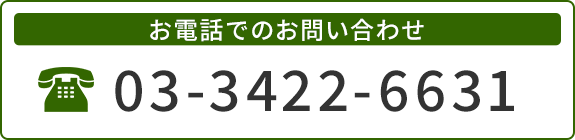よくある質問
Q 公正証書には、どんなメリットがありますか。
A 法律関係を明確にするだけでなく、強制執行認諾文言を付しておくと、裁判によらずに強制執行ができるため、貸金・養育費等の金銭の支払請求などの際に効果的です。
Q 契約内容を公正証書にしたいと思っています。ただ私自身は忙しくて行けない場合はどうしたら良いですか。
A 賃貸借契約、債務承認・債務弁済契約など契約についての公正証書は、原則として代理人を公証役場に出向かせて作成することができます。
ただし、任意後見契約については、性質上当事者においでいただくか、公証人が出張して当事者と直接会って作成する必要があります。
代理人を出向かせる場合、契約の相手方の関係者を出向かせると、法律上双方代理になってまずい場合が生じるので、できるだけ、出向かせる当事者側の人を代理人にするようにしてください。
代理人を出向かせる場合、委任状が必要になります。委任状の作成方法が分からない場合は、遠慮なく公証人にお申し出ください。
Q 遺言公正証書には、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べてどのようなメリットがあるのですか。
A 遺言公正証書には、次のようなメリットがあります。
- 遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が要求されるので、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、その方式を満たしていないとせっかく作っても無効になってしまうおそれがあります。これに対し、遺言公正証書の場合には、法律の専門家である公証人が作成するので、方式の不備で無効になるおそれはなく安心です。また、遺言の内容が複雑であっても法律的に整理した内容の遺言にいたします。
- 遺言公正証書の場合、原本が公証役場で厳重に保管されますので、改ざんのおそれや紛失の危険もありません。
- 遺言公正証書の場合、家庭裁判所の検認手続が不要となりますので、相続開始後、遺言の内容を速やかに実現できます。これに対し、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所に対し法定相続人全員の戸籍、除籍、住民票等の必要書類一式を出し、相続人全員が呼び出されて検認手続を受けなければなりません。
Q 私は公正証書によって遺言をしたいと思っていますが、病気のため入院中(自宅療養中)です。公正証書によって遺言ができますか。
A 遺言公正証書には、次のようなメリットがあります。
署名できない場合は、公証人が代署することもできます。
使者となってくれる人がいるのであれば、本人が相談・打合わせに来なくてもその人にどういう内容の遺言をしたいのか意向を伝え、使者を通じて公証人にご意向をお知らせください。
Q 不動産の権利書(登記済証又は登記識別情報)を紛失してしまいました。その不動産を売ることなり,公証役場に連絡するように言われたのですが,どのようにしたらいいのでしょうか?
A 不動産を売った場合,不動産の登記名義を売主から買主に変更する必要がありますが,そのような登記申請をする場合,不動産の権利証(登記済証又は登記識別情報)の提出が必要になります。
そして,権利証を紛失してしまったときは,原則として,登記官が,売主に通知をして本人確認をすることになります。
ただし,この登記官からの通知に代わる本人確認の方法がいくつか認められています。
その方法の一つとして,公証人が売主であることの本人確認をして,登記に必要な情報が記載された登記申請書に,公証人が認証(にんしょう)するというものがあります。認証とは,公証人がその書類に記載された署名や記名押印が本人のものであることを証明するものです。
認証にはいろいろな方式がありますが,この権利証紛失の場合は,売主が公証人の面前で署名又は記名押印するか,公証人に対し直接自分の署名又は記名押印であることを自認する必要があり,代理人による方式は認められません。したがって,売主本人が,公証役場にお越しいただく必要があります。
さらに,本人確認資料も厳格化されており,個人の場合は,
①発行後3か月以内の印鑑登録証明書と実印が必要であり,さらに,
②顔写真付きの公的な身分証明書(免許証やマイナンバーカード,パスポート等)でも確認させていただいています。
また,売主が,不動産登記簿上,所有者として表示されていることも確認しますので,
③発行から3か月以内の当該不動産の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)もご持参ください。
なお,④不動産登記簿上の住所と現在の住所が違うときは,その住所の変遷が確認できる資料もご持参ください。
売主が,ご自身で,登記申請書をご用意され,その申請書に公証人が認証をすることも可能ですが,登記申請書の内容等については,公証人は分かりませんし,関与しませんので,登記所や司法書士等の専門家にお尋ね下さい。
通常は,売主が登記申請手続を司法書士等の専門家に委任することが多いと思いますが,その場合は,
⑤司法書士等の専門家が作成した登記に必要な情報が記載された委任状に公証人が認証することになります。この場合も,売主が当該委任状に公証人の面前で署名又は記名押印するか,公証人に対し直接自分の署名又は記名押印であることを自認する必要があり,代理人による方式は認められませし,売主の本人確認資料も,さきほどと同じものが必要になります。
なお,お持ちの不動産を売ることになったときだけではなく,その不動産に抵当権等の担保を設定するときにも,同じような手続をすることができます。
しかし,当該不動産をお持ちのまま,特に取引などをしないのであれば,公証役場においてできることはありません。
詳しくは,司法書士や登記所にお尋ねください。
Q 割印(わりいん)の方法を教えてください。
A 別紙のとおり委任する旨の文言がある委任状に別紙を添付するなど,複数枚にわたる書類を一体にする場合,割印(わりいん)をする必要があります。
割印の方法は,次のようにしていただくことになりますので,参考にしてください。
⇒割印の方法は,こちら
Q 公証役場における事務の手数料は、どのようになっていますか。
Q 遺言公正証書の作成手数料のは,いくら位かかるのでしょうか。
A [遺言公正証書の作成手数料の概要について](令和7年10月1日改定)
1 遺言公正証書を作成する場合の手数料は,「公証人手数料令」という政令で定められています。
2 まず,遺言公正証書の基本的な手数料は,遺言により相続等させる財産の現時点の価格により算定します。
そして,相続等させる方が複数いるときは,それぞれの人に相続等させる財産の価格により算定した各手数料を,合計することになります。
例えば,遺言する財産の合計額が1億円の場合,
⑴ 妻だけに全て相続させるときの基本的な手数料は,4万9000円ですが,
⑵ 妻に6000万円,長男に4000万円を相続させるときの基本的な手数料は,妻の分として4万9000円,長男の分として3万3000円となり,合計で8万2000円となります。
3 さらに,遺言する財産の合計額が1億円以下のときは,基本的な手数料とは別に,1万3000円が加算されます。
4 そのほか,例えば,祭祀の主宰者(お墓や仏壇等を承継する方)を指定すると,基本的な手数料として1万3000円が加算されます。
5 また,公証人が出張して遺言公正証書を作成すると,基本的な手数料とは別に,日当(4時間以内は1万円,1日2万円)が加算されます。
そのほかに,旅費(交通費)の実費分も,必要になります。
なお,病床等に出張するときは,基本的な手数料が,その合計額の1.5倍になります。
6 さらに,遺言公正証書の枚数によって,手数料が加算されます。原本が,3枚を超えた枚数につき,1枚あたり300円が加算されます。そして,一般的に,正本相当と謄本相当の各1通ずつ(いずれも,法的には,原本と同じ効果があり,遺言の内容を実現することができるもの)をお渡ししますが,これらは,1枚あたり300円が加算されます。例えば,遺言公正証書の原本の枚数が6枚であれば,原本で900円,正本相当と謄本相当各1通には,正本相当・謄本相当である旨の各証明文書1枚が原本につきますので,7枚で,それぞれ2100円ずつとなり,合計5100円が加算されます。
7 そのほか,遺言公正証書を作成する場合,法律で,証人2人の立会が必要ですが,相続人の方等は証人になれませんので,適切な方がいないときは,公証役場で適切な人を紹介することもできます。そのときは,証人の方に,直接,謝礼を支払っていただくことになりますので,これらの費用も必要になります。
8 このようなことから,例えば,遺言する財産の合計額が1億円の場合で,妻に6000万円,長男に4000万円を相続させ,遺言公正証書の原本の枚数が6枚のときは,基本的な手数料が8万2000円となり,これに,3の1万3000円が加算され,6の5100円も加算されますので,合計で10万0100円になります。
そして,通常の出張の場合ですと,これに,5の日当として1万円が加算されますので,11万0100円になり,これに,旅費の負担も必要になります。
さらに,これらのほかに証人を依頼されたときは,その謝礼も必要になります。
なお,作成された遺言公正証書の原本は,公証役場で保管しますが,保管のための手数料は不要です。
8 このように,遺言公正証書の作成手数料は,誰にどの程度の価格の財産を相続等させるかなどによって,違いがありますので,遺言公正証書の文案ができないと,お伝えすることは困難です。ただし,大まかな目安としては,このような金額になります。
詳しくは,日本公証人連合会のホームページ「手数料」のページをご覧ください。
⇒こちら
Q 認証を受けた定款のファイルの内容を確認することができませんが,どのようにしたらいいですか。
A 認証した定款を保存した電子媒体等には,複数のファイルが格納されたフォルダがあり,認証文である公文書本体は、このうち,拡張子が「xml」となっているファイルになります。フォルダには,公文書を閲覧するための補助的なファイルも含まれますので,ファイルを移動する場合には,フォルダ内のファイルをすべて移動してください。XMLファイル形式の公文書を開くことができないときは,e-Gov電子申請のホームページ内のよくある質問のQ「XMLファイル形式の公文書ファイルを開く方法を教えてください」をご確認ください。こちら→